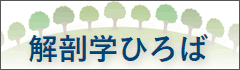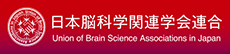学会について
About the Society
理事長挨拶
一般社団法人 日本解剖学会
理事長 仲嶋一範

日本解剖学会は、1893年に創立され、今年で132周年を迎える長い歴史と伝統を有する学会です。このような歴史ある学会の理事長にご選出頂き、その責任の重さに身の引き締まる思いでおります。
本学会は、解剖学に関わる研究と教育の両面から、その発展に貢献して参りました。
まず研究面では、全国学術集会に加えて各支部学術集会を開催しており、英文及び和文の学会誌の刊行など本学会独自の活動の他、国内外の関連学会との交流も積極的に進めております。国内では日本生理学会、日本顕微鏡学会、日本薬理学会など基礎系学会を中心に、最近は日本外科学会との連携協力も行っております。国外については、韓国解剖学会と正式な交流協定を結び、若手を中心に相互の学術集会にシンポジストを派遣するなどして、交流を深めて参りました。さらに、アジア太平洋解剖学国際会議(Asia Pacific International Congress of Anatomists)にも参加し、国際交流の輪を広げております。
さて、献体して下さったご遺体を使った解剖学の実習は、若い学生たちが医師や歯科医師となっていく上で、他に代え難い大きな役割を果たしております。人体の構造を深く学ぶことが医学や歯学を学ぶ基本になることは申すまでもありませんが、加えて、学生たちはそれが、自分たちのために無条件・無報酬で自らの体を提供して下さった篤志家による献体によって成り立っていることを知り、またその背後には、肉親の解剖を悲痛な思いの中承諾して下さり、帰りを待って下さっているご遺族がおられることを知ります。それをおぼえながら実習することにより、まさにsilent teacherから、学生たちは医師・歯科医師となる原点を学んでおります。教員や教材からではとても学べないものであり、篤志家やそのご家族の皆様には、ここに改めて深く感謝申し上げます。
本学会は、その大切な解剖学教育を担う教員や職員への支援を含む、篤志献体制度に立脚した教育研究体制の維持発展のための環境構築にも関わってきました。昨今は、従来の卒前教育に加え、卒後教育として需要が高まりつつあるサージカルトレーニング(外科手術手技修練)への対応など、解剖学教室の負担は増加しておりますが、健全な教育研究活動を維持するために、本学会としても様々な課題に引き続き取り組んで参ります。さらに最近は、解剖学実習やサージカルトレーニングといった既存の枠におさまらないご遺体利用についての議論が、サージカルトレーニングの監理・支援のための法人化の議論と並行する形で進んできております。本学会は、献体して下さった方やそのご遺族の願いに沿った形になるよう、篤志献体団体や臨床系学会、管轄省庁等と連携しつつ、慎重に、誠意をもって対応を進めて参りたいと考えております。
研究と教育の両面に関わる課題として、今期は特に若手研究者の更なる活性化のための支援に重点的に取り組みたいと考えております。本学会の今後の発展を期するためには、これからの学会を担うべき次の世代が、日本解剖学会を自分たちの学会として、自分たちのホームとして、自ら頑張りたくなるような学会になっていくことが重要だと思います。そのためには、研究奨励はもちろんのこと、解剖学の教育者としての支援も、キャリアを考えますと必要なことだと考えます。若手同士の交流や、若手とベテランとの交流を通して様々なアイデアを交換でき、互いに経験を共有できる、風通しの良い学会を目指していきたいと考えております。
生命の機能を支える組織構造の「かたち」を見て、その美しさと合理性に感動し、そのしくみを知りたい、解明してみたい、と思う。研究においてはそんな思いを若い人たちにも早くから経験して頂き、今の若手のさらに次の時代を担う人たち、学部生を含む若い人たちの本分野への更なる参入を図りたいと思っております。
是非会員の皆様からも忌憚のないご意見、ご指導を賜りながら、この歴史ある学会のバトンを引き継いで参りたいと存じますので、今後2年間、どうぞ宜しくお願い致します。