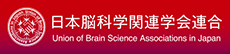凍結技法による観察を基盤とした動的組織構造の制御メカニズムの研究
帝京科学大学 医学教育センター
齊藤百合花

この度は歴史ある日本解剖学会において栄誉ある賞を賜り,大変光栄に存じます.選考委員の先生方をはじめとする日本解剖学会の先生方に厚く御礼申し上げます.今回,本稿の執筆機会を頂きましたので,僭越ながらこれまでの研究経緯を振り返りながら,研究内容について紹介させていただきます.
私は薬学部を卒業後,薬学系研究科の大学院に進学し,がん転移を主に研究する生化学系の研究室で博士号を取得いたしました.大学院では接着分子や遊走因子から,がん転移について主に分子生物学的な手法を用いて研究しておりました が,薬学部では組織学を学ぶ機会が無かったため,がん研究では必須の組織像を取得したり,正確に読み取ったりすることが難しく,研究室でともに研究する医師の大学院生などに教わりながら,研究を進めておりました.そのため,学位取得後,縁あって当時山梨大学の解剖学講座の1つである分子組織学教室を主宰されていた大野伸一先生(現 山梨大学医学部名誉教授)の元に助教として任用いただき,「組織学や人体解剖学についてはゼロから教えますよ」とおっしゃっていただいたことは,非常に心強く,楽しみで仕方なかったのを今でも覚えております.ちょうど大学院に山梨大学を卒業した医師の大学院生がおり,大野先生の教え子ですと言われ,その人となりや実習の厳しさをうかがいましたが,「大野先生ならきっと大丈夫!」と太鼓判を押していただいた通り,山梨大学に着任後は,大野先生をはじめとして研究室員から親切にしていただき,研究に教育にと楽しい解剖学三昧の日々を送ることができました.大学院までは当たり前ではなかった,しかし解剖学では当たり前の“構造を見る”ということが,私にとっては非常に興味深く,感動した当時の思いは,今現在でも続いております.
大野先生は当時,生体内凍結技法やクライオ生検法による組織標本作製法を開発されており,私に最初に与えられたテーマはクライオ生検法を使い,肝臓について研究して下さいというものでした.クライオ生検法は臨床でも利用される生検に生体内凍結技法と金属圧着法を組み合わせた方法であり,生体内凍結技法の利点である瞬時に凍結することによる血流を維持した状態の組織像を得られることに加え,生検の利点である複数箇所や時間差による組織採取を可能にしたものです.これらの特徴を生かし,虚血再灌流に近い状態にしたマウスの肝臓において,古典的肝小葉やZone分けに依存しない新たなグリコーゲンの消費領域を発見した時は,生体内凍結技法やクライオ生検法の凍結良好部位の特徴の1つである,美しい組織像に感謝しました.このテーマでは,グリコーゲンの他にも血漿中のアルブミンやIgGなどを組織切片上で可視化し,傷害された細胞の特定なども行っています.また,肝臓のテーマを終えた後は,興味のある臓器をテーマにして良いとのことでしたので,大学院の頃にテーマの1つとしていた,がんの肺転移に関わる研究をすることに決め,まずは肺の呼吸による動きと血流の可視化に取り組みました.生体内凍結技法は血流の維持に加え,肺の呼吸による肉眼的な動きを保持することも可能であったため,肺胞壁の伸縮を組織切片上で見分けることのできる標本の作製に成功しました.更に血流に蛍光物質を注入した状態を秒単位で止めた標本を作製することも可能であったため,肺の組織切片上で細動脈と細静脈が交互に規則正しく配置することも明らかにしました.この論文については,米国の組織化学会の懇親会に出席した際に偶然話しかけた先生から,自分がレフリーをしたが,とても美しい図だったので,雑誌の表紙に推薦したとおっしゃっていただき,嬉しかったことを覚えております.またその後,目標としていたがんの肺転移の初期過程である癌細胞の肺胞毛細血管壁への接着,凝固因子の段階的な変化,血小板の凝集や活性化などについても,組織切片上で可視化することができました.ただ,学生実習で見せる肺の組織像に比べて生体内凍結技法で得られたマウスの肺の組織像があまりに美しく,組織構造の理解を深めるのに非常に有用であると分かりながらも,実習の都合上,生体内凍結技法による肺組織標本を見せられる機会がなかったことは残念であったかもしれません.
山梨大学で勤務している際に,自分の研究を進める以外にも他の教員や大学院生の研究を手伝うことも増え,様々な臓器の物質の動きや組織構造の動きに興味を持つようになりましたが,その過程で出現した疑問が末梢神経はどのように伸縮するのかということでした.四肢に代表される骨格筋が伸縮する際に,それを支配する末梢神経が全く伸縮しないとは考えづらかったためです.この疑問を解決するために,生体内凍結技法を用いて後肢を伸縮させた状態の組織標本を作製して観察したところ,後肢を弛緩させた状態では神経線維は棒状であるのに対し,伸展させた状態では神経線維が数珠状になることが明らかとなりました.また,数珠状になった神経線維のくびれ部位に末梢神経特有の構造であるシュミット・ランターマン切痕が位置する確率が高いことも突き止めました.このことから,シュミット・ランターマン切痕が末梢神経の伸縮に関わる動的組織構造であることが示唆されました.シュミット・ランターマン切痕は髄鞘中に細胞質が残存してコイルバネ状構造を取ることでわずかに伸縮し,神経線維がちぎれないようにしていると考えられます.また,シュミット・ランターマン切痕には様々な接着分子や細胞骨格などが抱負に局在していることからも,構造を維持しつつも柔軟性を保つことが可能であると考えられました.この末梢神経とシュミット・ランターマン切痕に関わる研究テーマについては,現在所属する帝京科学大学に異動後も継続して行っております.
帝京科学大学に異動後は,まずシュミット・ランターマン切痕の構造がどのように制御されているかに焦点を当て,シュミット・ランターマン切痕に局在する分子のうち,接着分子であるCell adhesion molecule 4(CADM4),膜骨格蛋白である 4.1G,シグナル蛋白であるmembrane palmitoylatedprotein 6(MPP6),足場蛋白であるLin7 が蛋白複合体を形成していることを明らかにしました.これらの蛋白のうち,4.1Gを欠損したマウスを用いて解析を行ったところ,4.1G欠損マウスの末梢神経ではシュミット・ランターマン切痕は形成されるものの,CADM4,MPP6,Lin7がシュミット・ランターマン切痕に局在しないこと,シュミット・ランターマン切痕が長軸方向に短くなることが分かりました.また,シュミット・ランターマン切痕以外にも髄鞘が過形成になったり,傍絞輪部が膨化したりすることから,4.1G自体がシュワン細胞全体において主要な役割を持つことも明らかとなりました.さらに,4.1G欠損マウスでは,加齢マウスにおいて,運動負荷をかけることにより運動機能が低下することも明らかにしました.シュミット・ランターマン切痕における蛋白複合体の機能をさらに解明するため,MPP6欠損マウスを作成して解析を行ったところ,MPP6欠損マウスではシュミット・ランターマン切痕にCADM4 および 4.1Gが局在し,Lin7のみが消失したことから,4.1G はCADM4 およびMPP6をシュミット・ランターマン切痕に運搬し,MPP6はLin7を運搬することが明らかとなりました.現在はこれらのマウスを用いながら,シュミット・ランターマン切痕を主体に,末梢神経自体の機能に及ぼす影響を検討しております.
また,帝京科学大学に異動してからは理学療法士などリハビリテーションに関わる資格取得を目指す学生の解剖学教育に関わるようになりましたので,末梢神経の動的組織構造の制御メカニズムを明らかにしつつ,リハビリテーションを考慮した検討も行っていきたいと,日々楽しく奮闘させていただいております.引き続き,教育と研究に励み,微力ではございますが解剖学会の発展に貢献してまいりたいと存じます.解剖学会の諸先生方におかれましては,今後ともご指導ご鞭撻のほど,どうぞよろしくお願い申し上げます.
謝辞
解剖学の世界にお導き頂き,教育および研究について熱心にご指導くださった大野伸一先生を始めとし,山梨大学から現在に至るまで長きに渡りご指導いただいております寺田信生先生(現信州大学教授),大野伸彦先生(現自治医科大学教授)に深謝申し上げます.また,山梨大学教授 竹田扇先生および小田賢幸先生におかれましては,山梨大学に所属しておりました際に,先生方の御厚意により解剖学教育において手ずからご指導いただきましたこと,この場をお借りして心より御礼申し上げます.
(このページの公開日:2021年12月17日)