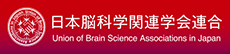肝星細胞の発見者 カール・クッパーの生涯*
東京医科歯科大学 名誉教授(解剖学)
和氣健二郎 訳

* 訳出した原著はKarl v. Kupffer mit Portrat. Arch. fur mikr. Anat 62:669-718 (1903) に掲載された追悼文で,著者名はない.訳文の一部を省略した.人名は日本語とし,必要に応じて訳注として欧語氏名,年代,説明文を加えた.肖像は原著の写真にクッパーの署名を重ねて作成した.
カール・クッパーは1829年11月14日,クールランド(現在はバルト3国の一つ,ラトヴィア)の小さな町レステンで,新教の牧師カール・ヘルマン・クッパーの長男として生まれた.一家は牧師館に住み,家畜舎や納屋のある広い裏庭は森と湖に囲まれた牧草地へ続いていた.カールはフランス語の素養を近くの男爵家に住む家庭教師から学んだが,ギムナジウムの全教科は父が教えた.19歳になったカールは1848年のクリスマス前にドルパト大学(現在名:タルトウ大学)の入学資格試験に合格し,医学部学生に登録された.熱心に学ぶ傍ら青春を謳歌して学生生活を終えると,学位試験に合格,1854年に医学博士号が授与された.学位論文は「カエルの脊髄組織,とくに灰白質固有の性質について」で,指導教官は当時,生理学兼解剖学の教授で,医学部長でもあったビダー訳注1)であった.この論文には,当時の学会で議論の的になっていた二つの命題,1)脊髄の構築における結合織の役割と,2)脊髄前根の神経線維は前角神経細胞の突起なのか? が含まれていた.
学位を取得したクッパーはレステンへ帰郷し,開業医として働き始めたが,その仕事は彼を満足させなかった.ちょうどその頃ビダーから解剖学教室の助手になる気持ちはないか,という問い合わせがあった.感謝してドルパトに戻ったクッパーは,1855年3月に助手兼プロゼクトール(解剖技師)に任命された.
クッパーの復帰第1報はビッダーとの共著,「脊髄の構造とその構成要素の発生に関する研究」(1855)で,大きな反響を呼んだ.論文の冒頭でビダーは「この発生の部分はクッパーが独自に研究したもので,まだ十分に纏まっていないが,中間報告として報告する」と断っている.この研究を短期間に発表まで漕ぎつけたのは,翌年5月にクッパーの留学が決まっていたからである.
この論文内容はケリカーの『発生学』(第1版,1861)のなかで詳しく紹介された.脊髄の発生初期に先ず灰白質が生じ,そのあとで白質が出現すること.白質は細線維で構成され細胞核を含まないこと,また最初に前索と側索の均質な原基が発生し,後索は後根の出現とともに発達することが強調されている.クッパーは後根線維が後索中を上行するものと考えた.また前根線維は脊髄前角の大型神経細胞の集団から出ることも観察している.この所見は「後根は全て灰白質内の細胞の出口」とするビダーの説と真っ向から対立していたため,クッパーは共著者にしてほしくなかったと想像される.
クッパーのもう一つの新しい所見は,神経細胞と軸索との関係である.当時は細胞連鎖説Zellkettentheorie が一般に受け入れられていた.その根拠のひとつにシュワン鞘の核間距離がほぼ一定であることが挙げられていた.クッパーは後根や白質内の線維束中に神経細胞の核が見られないことから,この説に反対し,「神経細胞には自己の細胞突起を長く延ばせる特性があるため,神経線維は神経細胞の長い突起と見なすことができる.その後に軸索間に出現する芽細胞から疎性結合組織と原始的な鞘や髄鞘が形成される.」と述べている.このクッパーの見解は後になってヒスによる神経発生の観察により支持されて神経学の一つの基盤となった.
ビダーは将来自分の解剖学教室を生理学教室にふりかえ,クッパーを生理学教室の後継者にしたいと密かに考えていた.クッパーの留学は生理学の基礎的知識を習得させるという指導者としての親心からであった.
クッパーが西ヨーロッパ留学の途についたのは1856年5月であった.ケーニッヒスベルグ,ライプチッヒ,ヴユルツブルグを経て,ウィーンにしばらく滞在,ブリュッケとルードヴィヒを訪ね,ついでベルリンではデユ・ボワ・レモンとミュラー,ゲッチンゲンではヴァグネルと多くの碩学の講義を熱心に聴講した.このほぼ1年半の留学期間にクッパーは3編の論文を発表している.(1)腸の運動に対する迷走神経と内臓神経の作用,(2)電気ウナギの電気器官について,(3)筋の局所的興奮に対する抑制能について,である.
クッパーはこの短い留学期間に,かなりの業績を挙げたにもかかわらず,それ以上に生理学の分野へ深く分け入る意欲はもはや萎えていたのである.その理由は自分には緻密性が要求される分野に向いてないのではないかと不安を覚えるようになったこと,またベルリンでヨハネス・ミュラー訳注2)から受けた比較研究の影響が余りにも大きかったことが挙げられる.
そのようなクッパーにとって幸いなことには,1857年12月にドルパトに帰国すると直ちに,解剖学の准教授兼プロジェクトールに昇進することになった.この事情を少し説明する必要があろう.ドルパト大学の解剖学教授ライヘルトが1853年に退職したので,生理学教授であるビダーが解剖学の講義・実習や教室員の指導を兼任していて多忙であった.そこで弟子のクッパーに仕事を手伝ってもらう必要が生じたのである.
その最中にクッパーは父の訃報を聞く.同時に,残された家族の面倒を見なければならなくなった.それでも彼は与えられた公務を懸命に果たした.自由な時間ができると,比較解剖学や動物学の勉強に当て,ベルリンで受けた刺激を忘れることはなかった.クッパーは周囲の環境と闘いながら,その分野の材料をできるだけ多く収集し,その結果をいくつもの速報として発表した.
続いてクッパーは羊の胎仔を用いて腎臓の発生研究に着手した.材料を重クロム酸カリ溶液で固定後,フリーハンドで40~50μmの厚さの連続切片を作製した.この標本から,「腎の原基はウオルフ管の後壁に存在する盲嚢」という重要な発見をする.この研究を始めた動機は腎臓も膵臓や肺と同様に腸から発生するというレマーク訳注3)の見解に疑問をもったからである.クッパーは腎細管は腎杯とその分枝(集合細管)とが別々に発生し,その両者が連結して尿細管ができることを発見した.この発見は,「腎管系は全て腎路から発生する」という従来の学説と鋭く対立し,双方の支持者の間に激しい論争が沸き起こった.
このような経験を通じて,クッパーは自分が選んだ分野でも充分やっていけるという自信をもつことができた.ヨハネス・ミュラーの比較生理学から影響を受けた比較発生学は系統発生の諸問題を解く有力な武器になったし,また比較発生学は自由にアイデアを考えさせる様々な興味深い課題を提供することにもなった.
ほかにもドルパト植物園の池から採取したユスリカの卵の研究がある.彼はこの属の昆虫の特殊な胚膜に興味をもった.この膜についてはワイスマン訳注4)が記載しており,メチニコフ訳注5)が高等脊椎動物の羊膜との比較を研究していた.クッパーは生きている卵で胚膜が折り畳まれる過程を観察し,図を添えて正確に記載した.注目すべきはこの論文の最後に昆虫の胚膜と有羊膜類の羊膜との比較について彼の見解が述べられていることである.この研究がクッパーのドルパトでの最後の仕事になった.
1865年8月,クッパーはリガとベルリンを経由してキールへ向かう旅に出た.この旅には深い理由があった.すでに述べたように,ビダーは欠員になっていた解剖学教授を兼任していたが,1862年に解剖学教授にライスネル訳注6)が就任した.このことはドルパトの解剖学教授の地位を密かに望んでいたクッパーにとって大きなショックであった.一方生理学に対する彼の情熱は薄れるばかりで,ビダーの後継者として生理学教授のポストを受ける気持ちは更更なくなっていたのである.その上家庭の経済的な事情もあった.こうしたことから,解剖学准教授兼プロジェクトールの地位を放棄する決心を固めたに違いない.彼はすでに上級公務員採用候補者や宮廷顧問官,さらに大学中級教員にも任命されていたのであるが.
この苦しい選択には他にも理由があった.西ヨーロッパに留学した際,見聞した躍進する科学がいつまでも印象に残っていた.また彼自身が吐露したように,東方の大陸に対する嫌悪感から,1860年にケーニヒスベルグ科学アカデミーから解剖学・生理学助手に採用するという招待を受けていたのであるが,それを断っていたのである.この招待は先輩のフォン・バワー訳注7)の好意によるものであったが,これを断ったことにバワーは驚きをかくせなかった.
クッパーは1865年の年頭から長患いをし,数ヶ月間の静養を余儀なくされ,その年の12月31日に依願により職を解かれた.大学当局はクッパーの業績と勤務の功績を讃えて,年報714ルーブルに当たる退職金を給付した.
自由の身になったクッパーは以前から望んでいたキールのドイツ北極探検準備委員会会員に志願した.キールでは古くからの友人ヘンセンと再会した.当時ヘンセンは生理学の私講師をしていた.ヘンセンはクッパーにキール滞在中は自分の研究室を使ってもいいと言ってくれたので,その好意に甘えることにした.クッパーは北極探検隊長,プロシアの海軍少佐ウエルナーに会い,自分を医師兼動物学者として任務させてほしいと願い出て,その約束をとりつけた.しかし翌年5月に再びキールを訪れたときに,オーストリーとプロシアの戦争が勃発し,そのために北極探検は中止になってしまった.クッパーはヘンセンの助言を受けキール大学に留まることにし,教授資格試験を受験して合格,1866年5月5日に組織学の私講師の職につくことができた.
こうしてクッパーはキールの地で再びエネルギッシュに研究を開始した.ドルパトで次は魚類を用いて腎発生を研究したいと計画していたので,その材料はキール湾で容易に入手できた.6月から7月にかけてトゲウオの卵の発生を研究し,Arch. f. mikr. Anat 第2巻に「硬骨魚類の尿膜」と題して発表した.1868年の夏には海藻が生い茂った場所で沢山のホヤが採集できたので,当時評判になっていたコワレフスキー訳注8)が1866年に行ったミミズの実験をホヤを用いて追試してみることにした.その内容は変態による退化過程を経て完成に至る過程を観察したもので,論文3編に纏められた.この内容を「動物界に於ける進化と退化」と題してキール市民向けの講演会で講演した.
クッパーは魚類やホヤの研究が一段落したので,新しく組織学の課題にとりかかった.それはタケフシムシ(Blatta Orientalis)の唾液腺と神経線維との繋がりに関する研究である.この研究を始めた動機は,新しく出版されたストリッカー(1871)の組織学ハンドブックに掲載されたプフリューガーの記載であった.当時唾液の分泌に対する神経の影響についてハイデンハインとプフリューガーの仮説があり,神経の終末が腺細胞に結合しているというものであった.その記載にクッパーは満足していなかった.神経終末が唾液腺細胞の内部にまで侵入して,細胞核周囲に「神経線維網」を形成すると考えていたからである.これに対してハーファーは神経が腺組織へ侵入することは認めるとしても,核の周囲に線維網を形成することは多分アルカリ処理によって生じた人工産物であろうと反論していた.1875年にクッパーは別の仕事で「動物組織の細胞における細胞質の分化について」を発表していた.この研究はフレミング訳注9)よりも早く細胞質内に特殊な網状構造を記載した研究ではないか,と評判になっていた.本来細胞質は均一または顆粒状と考えられていたが,クッパーはカエルの肝細胞で2種の異なる細胞質を記載していた.その一つは硝子様で,他は散在性で微細な線維状であった.前者は核の周囲に緻密性に富む中心塊があり,その部位は網状に組織化された網工を形成していた.彼は硝子様の細胞質を原形質Protoplasma,網工状の細胞質を副形質Paraplasma と命名した.両物質は化学物質に対して異なる反応を示し,前者は加熱により物質を輸送する性質をもつようになる.このような性質は新鮮な細胞で顕著であった.このクッパーの図はヘルマンのハンドブックに掲載されている.
以上のような背景のもと,クッパーは神経線維と腺細胞との関係を明らかにしたいと考え,肝臓で両者の関係を観察したいと考えた.しかしその試みはすぐには成功しなかった.神経を染める目的で鍍金法を何度も試みたが,徒労に終ろうとしたとき,偶然に肝小葉内で毛細血管(類洞)の外側に塩化金で黒化する星状の細胞を発見することになる.早速この細胞を‘Sternzellen der Leber’(肝臓の星細胞)と命名し,1876年ワルダイエル教授への書簡報告として発表した訳注10).発見の当初,彼はこの細胞は神経性細胞ではないかと考えていた.ところが1884年にアッシュがボン大学の学位論文で,星細胞の細胞質中に様々な封入体がよく観察されるという報告訳注11)に接したクッパーは自分の観察に疑問を覚えるようになり,1899年になって訂正論文を発表した訳注12).マイヤーはAnat. Anz. 誌のなかで,クッパーの見解を示す2,3の主張を彼の論文から引用し,この報告の正当性と,その研究の価値は決して消え去るものではないだろう,と記している.
キールにおけるクッパーは1866年の夏学期に大学教授資格を取得し,続いて冬学期には『無脊椎動物の動物学』と『感覚器官の解剖学と組織学』を講義した.解剖学の主任教授はベーンであった.翌年の夏学期にはベーン教授は講義担当の教授職から外れることになった.ベーン教授の突然の休職には政治的な理由があった.シュレービヒ・ホルシュタインがプロイセンに併合されると,その行政は忠誠を誓ったプロイセンへ委譲された.その実施に当ってベーンに教授職を委ねることは難しくなり,ベーンはその地位を去らねばならなくなった.翌年解剖学教室と動物学教室が分離し,メビウスが動物学教室の主任教授としてキールへ招聘されることになった.クッパーは記載解剖学と組織学を講義し,発生学はヘンセンが担当することになった.クッパーに割り当てられた部屋は,講義室,解剖実習室,顕微鏡実習室,教授室兼教授実験室の4部屋で,その冬学期の受講学生は15名であった.クッパーは解剖遺体と研究室の不足を訴えたが,その実現はすぐには解決しなかった.その後8年が経過した年の大学年表には次のような記事がみられる.
「解剖学の主任教授カール・クッパー博士が,この冬にケーニヒスベルグ大学から招聘を受け,東方へ移られることになった.それは医学部のみならず大学全体にとって至極残念なことである.同教授にとって新しい職場が幸せな未来を約束するものであるよう,また彼の地においても,われわれの大学に対する思いが決して褪せることのないように祈る.クッパー教授は1872~74年の2年間,学部長に就任し,その間に当地に講堂が創設されたことを付言しておきたい」このような心のこもった送別の辞にみる特別の名誉は,つぎのクッパー自身の送別の挨拶にも表れている.「キールで私は生涯で大変幸せなで楽しい時期を過ごすことができた.この町も地域も魅惑に富み,ホルシュタインは私にとって第二の故郷と思っている.ドルパトに続いてブレスローからもお招きをいただいたが,いずれもお断りさせていただいた.しかし11月にケーニヒスベルグからお招きを受けた際は,経済的な理由からお受けすることにした」この経済的な理由とは,クッパーは1869年5月15日に,友人のキール大学眼科教授フェルケルの妹,イダ・ゴルドマンと結婚したことである.1870年に長男が,その翌年に長女が誕生した.クッパーはその長男の名前に,同年亡くなった弟の名前をとってグスターフと名付けた.弟はクールランドの開業医であったが,その職業の犠牲になったのである.彼は素晴らしい性格で,どんな時でも忘れ難い印象を残した.クッパーは弟を失ってから心が癒されることはなかった.
クッパーは1876年4月にケーニヒスベルグに赴任した.ケーニヒスベルグの解剖学教室は当時としては記載解剖学と比較解剖学の価値ある多数の収集標本で有名であった.一方組織学の講義に必要な標本は不足していた.そのため組織学の講義時間を減らさねばならず,担当していた生理学のグリユーンハーゲン私講師にやむなく退職してもらうしかなかった.その時間を比較解剖学の講義にふりかえ,キールから一緒に移ってきた私講師アルブレヒトを准教授兼プロジェクトールに昇任させ担当させた.その翌年にはベネッケが准教授に昇進し,1879年に新たにベームを助手に採用した.ベームはラウバーの弟子で,卓越した能力,奉仕の精神,組織学の豊かな知識の持ち主であった.彼の手によって組織学の教材は急速に充実した.ベームはクッパーの生涯を通じて,精神的,技術的に大きな支えになったばかりでなく,素早い仕事ぶりや豊かなアイデア,文献の抜群の記憶力でクッパーの研究に計り知れない恩恵を与えた.クッパーはもはや標本作製に時間を費やす必要もなくなり,研究に専念できた.
クッパーは4年間のケーニッヒスベルグ在職期間に多数の論文を発表した.前任者のミュラーは当地で容易に入手できる円口類を材料にして受精を研究していたので,クッパーもその貴重な材料に興味をもち,ベネッケと共同で追試することにした.
ここで記憶に留めておくべきことは,当時オスカー・ヘルトヴィヒの受精に関する報告が多くの形態学者の注目を集めていたことである.「受精とは2コの生殖細胞核の融合に基く」という事実から,卵細胞の中へ第2の核が侵入する経過が研究者の興味をかき立てた.ヘルトヴィヒは卵細胞中へ精子の頭部のみが侵入し精子核の起源になるとした.この見解はビュッチェリの説を踏襲するものであった.当時の常識では受精には1コの精子のみが関与し,ポリスペルミーは異常とされていた.クッパーはこの考え方には同調できなかった.彼の円口類の観察では一番早く卵細胞に到達した精子が卵黄中に侵入する.しかし,それですべては終了せず,続いて卵膜と卵黄との間にできた細胞質の間隙(受精丘)の中へ後続の精子が迎え入れられ,その後に受精が起こるとした.従って受精現象には卵黄にも積極的な働きがあるとし,それを二次的な受精現象と考えた.このようにクッパーは受精過程に最初に精子の,ついで卵子の作用という2段階に分ける考えに至った.その受精丘は卵膜が内部から押し上げられて形成される.その内部では卵膜を突き破って侵入した精子がなおも運動を続けている.クッパーの受精に関する一連の研究は,とりたてて重要な結果をもたらすものではなかったが,受精における卵黄の活動性とポリスペルミーについては,後年,他の材料でも証明された.
1880年,クッパーはシャフハウゼンの編集による膨大な人類学資料報告の第IV 巻に,医学部卒業試験受験生ベッセル-ハーゲンと共著で,ケーニヒスベルグで収集した人類学資料の頭蓋と体骨格について報告した.同年に行われたカントの墓所訳注13)の再調査では,カントの頭蓋の人類学的価値をベッセル-ハーゲンとともに調査した.その結果は翌年発表された.クッパーはケーニッヒスベルグで同僚との交友関係に恵まれたが,その都市には慣れ親しめなかった.東方に対する彼の嫌悪感は強まるばかりであった.
1880年の6月,クッパーはミュンヘン大学からビショッフ教授の後任として招聘があり,受けることにした.東方に対する個人的な嫌悪感から開放され,同時に長年の希望が漸くかなえられるという理由からである.ミュンヘンではクッパーは組織学と発生学の講座を,ときには記載解剖学や局所解剖学も担当することになった.当初は不慣れな南ドイツの慣習に戸惑うことも多かったが,いつしかそれにも親しみを覚えるようになった.ミュンヘンでも引き続いてチョウザメの膵臓と脾臓の発生について研究した.
ミュンヘン時代のクッパーは,図式化された考えに嵌り込み,そのアイデアを大胆に論文化することに熱心である反面,熟考を重ねて最終的に正鵠な結論へ導くことに欠く傾向が見受けられる.この傾向は次第に強くなり,自己のアイデアが先行してドグマ的になり,事実の観察よりも,むしろ都合のよい考察が主体になっていった.ミュンヘン時代の最後の十年間に彼が主として行なった頭部の発達に関する研究にも,その傾向が如実に現れている訳注14).クッパーのミュンヘンでの活躍は学術研究以外にも多方面に亘っていた.彼は優れた教師でもあり,稀にみる修辞能力によって最初の2ヶ月間に講義の聴講率は高いレベルに達した.講義は彼にとって興味ある仕事であったし,小細工を弄して聴講生を増やそうとするようなものではなかった.精査した教材をフルに活用したクッパーの講義は一人の舞台監督のような能力を発揮し,黒板に描く美しい模式図は聴講する学生の理解を大いに助けた.講義の冒頭にクッパーが学生に向かって発する第1声はいつも“Kommilitonen!”「学友諸君!」であった.
クッパーの講義はレベルが高く,初心者に十分理解させない嫌いがあったものの,彼の卓越した能力はすぐに伝わった.彼は学生に難しい問題に対して理解させようとしたばかりでなく,興味を持たせようとした.クッパーの講義には毎年細やかな配慮によって新しい観察と考察が取り入れられていた.講義室の壁には多数の模式図が掲げられ,講義が終わるとデモを行い講義内容をよく理解させた.
ここでミュンヘンの形態生理学会に対するクッパーの活動について触れておきたい.クッパーは常に学会に心血を注ぎ,「講演の夕べ」に出席して,会の学術的評価の向上に務めた.集会においてクッパー自身が心がけていたことは,第1に自分自身が模範的な例を示すこと,第2に目的にかなった批判をすることであった.賛成するにせよ反対するにせよ,クッパーのように心くばりをもって上品に,それでいて効果的に発言することは容易なことではない.彼は自分自身が,また教室員たちが研究成果を少なくとも年に一度は学会で報告することを義務にしていた.クッパーは学会会員に対して新しく重要な問題について批判的に紹介することに時間と労力を費やすことを決して厭わなかった.クッパーは極めてデリケートな感情の持ち主で,講演は受講者の状況や立場をよく理解したものであった.クッパーは同じ道を歩む人たちの中で,常にトップにいたいという強い意志をもっていたことは間違いない.
クッパーはドイツの政治にも興味をもつようになった.ドイツの産業が一層繁栄するには植民地政策が必要とされた時代にあって,彼は思慮深さと青年のような情熱をもってこの問題にも立ち入った.ミュンヘンでは長年ドイツ植民地団体支部長を務め,その功績はクッパーの墓石にも刻されている.
クッパーの個人的な交際では,最初は親しみ難く打ち解けないように見えるが,根は極めて温かい人であった.機嫌がよいときは,軽い冗談を言ったりもしたが,それは彼の得意とするところであった.議論が伯仲した場合でも不愉快な気持ちにさせるようなことはなかった.
最後にクッパーの研究について考えてみると,その学風は強い連続性に特徴付けられる.クッパーにとって研究が全てであった.クッパーのように,研究者の教養によって,その研究と教育に美しさを覚えさせることは稀なことである.クッパーはよく書かれた論文を読むことを好んだ.彼の話はしばしば研究の話に始まり,次いで詩の朗読へと続いた.彼は研究が彼の全ての行為の礎石になるように務めた.現在では建築物の小さな部分の構造が研究されているが,当時の研究では建築物全体の設計図が彷彿されなければならなかった.多くの空中楼閣を建てることは必ずしも害になるものではない.
クッパーは最後の年月を田舎で静かに過ごすことを望んでいた.しかしそうにはならなかった.というのはヘルトウィッヒのハンドブックに「中枢神経系の発生」の執筆を依頼されたからである.1901年10月,クッパーはミュンヘン大学を辞し,この生涯最後の仕事にとりかかった.翌年9月19日に脳卒中の発作が襲い,12月16日に肺炎を併発して亡くなった.さまざまな意味において真にドイツ人らしい一人の学者が,その国の研究レベルを向上させて静かにその生涯を閉じた.
【訳注】
- Georg Friedrich Karl Heinrich Bidder(1810~1894) ドルパト大学生理学教授.1853~1857年に解剖学教授を兼任した.交感神経系の機能上の独立性を明らかにし,消化管瘻を作り消化液と代謝の研究へ道を拓いた.和氣健二郎,Piret Hussar,佐藤秋絵,井上孝二,佐藤哲二(2010)
タルトウ(ドルパト)大学Anatomical theater の解剖学者たち.解剖誌 85:91-96.参照 - Johannes Muller(1801~1858)ベルリン大学生理学教授,生物学探究における比較研究の重要性を強調,実験生理学,比較解剖学,組織学,発生学,比較解剖学,海洋動物,古生物学など広範囲に及ぶ.
- Robert Remark(1815~1865)固定剤,発生,細胞分裂,神経突起を研究.
- August Weismann(1834~)医師として働いていたが,ロイカルトの研究室で2ヶ月過ごし顕微鏡の虜になる.1866年フライブルグ大学動物学教授.発生学,とくに昆虫の変態について研究し,その初期の論文にはチャールス・ダーウインの序論が付され,英訳された.
- Elie Metchnikov(1845~1916)ロシアのハリコフ近郊で生まれ,ハリコフ大学で動物学を学んだ後,ロイカルトのもとで研究し,プラナリアの細胞内消化の研究がマクロファージの発見に繋がる.著作[炎症の比較病理学講義]
- Ernst Andreas Reissner(1824~1878)ドルパト大学に学び,学生時代からライヘルト教授のもとで内耳の構造を研究し,Reissner膜を発見した.ドルパト大学教授に昇進後にヤツメウナギの脊髄中心管内にReissner’s fiberと呼ばれるひも状物を発見した.
- Karl Ernst von Baer(1792~1876)ドルパト大学で医学を学び,卒業後もドルパトで研究した解剖学者,発生学者.ケーニッヒスベルグで教鞭をとる(1817~1834).イヌの卵巣のグラーフ濾胞中に卵子を発見した.
- A. Kowalevsky,ミミズでは,第1次中胚葉細胞が長軸方向に並び,その成長していく先端は一個の大きな細胞であり,そこから他の全ての細胞が一連の不等細胞によって千切れてできることを発見した.そのような細胞は後に「端細胞」’teloblast’ と呼ばれるようになった.
- Walter Flemming(1843~1905)1850年代は固定法や染色法が改良され,細胞質と核を詳細に観察できるようなったが,その最初の研究はフレミングによる核分裂へ導く諸変化の観察であり,近代細胞学の幕明けと言われる.
- 和氣健二郎(1978)星細胞発見のKupffer の原著.解剖誌 53:368-372.参照.
- Ernst Asch (1884) Ueber die Ablagerung von Fett und Pigmentin den Sternzellen der Leber. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde vorgelegt der hohen medizinischen Facultat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms - Universitat zu Bonn.
- クッパーがミュンヘン大学教授に就任後1898年にキールで開催された解剖学会で,「星細胞は特殊な類洞内皮細胞で墨を貪食する細胞」と「訂正」した.その内容は1899年に膨大な論文として発表された.和氣健二郎(1975)肝臓の星細胞 科学(岩波) 45:33-42.参照.
- Immanuel Kant(1724~1804)ケーニッヒスベルグで生まれ,ケーニスベルグ大学の論理学形而上学教授.代表的著作は『純粋理性批判』(1781).カントの遺骸は再調査の1880年以降,大聖堂近くの簡素なゴチック風の教会の下に埋葬されている.
- このクッパー晩年の傾向は肝星細胞の「訂正」論文(1899)にも認められる.和氣健二郎.Browiczの食細胞とKupfferの「いわゆる星細胞」解剖誌 84:17-21(2009)参照.
※著者による字句の修正が含まれています
(このページの公開日:2020年10月1日)