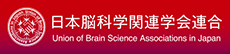解剖学という基礎
東京大学名誉教授
養老 孟司
方法としての解剖学
解剖学は基礎中の基礎だ.学生時代にそんなことをよく聞かされたような記憶がある.本当のところ,ピンと来なかった.自分なりにそうだと思えるようになったのは,研究生活を続けて何年もたち,自分で本を書くようになってからである.最初の本は『形を読む』(培風館)だった.乱暴にいえば,解剖学は対象の形を見て,それを解釈する.そこには限られた数の特定の視点がある.あるいはそれだけしかない.そういう内容だった.
学会に出席して,質疑応答を聞いていると,それがわかる.質問者はどれかの視点から,訊いているからである.その意味で,質疑が視点から分類できることに気づいた. こういうこと自体は,解剖学か,否か.「あんたの言うことは哲学だよ」とよく言われた.ソクラテスの論法を使えば,そう言っている人は「哲学とはなにか」を知っている.でも私は知らない.解剖学教室には27年勤務したけれど,その間,哲学を学んだわけではない.曲がりなりにも解剖学をやっていたのである.
解剖学教室を辞めて,さまざまな本を書いた.でもそこに一貫しているのは,解剖学で学んだ考え方である.そう思わない人が多いことはわかっている.まずそれを説明してみる.近代日本の諸科学は対象によって分類されるのが普通である.法学は法律,経済学は経済を学ぶ.臨床医学はさらに極端に分けられるようになった.眼科,耳鼻科はもともとだが,肝臓,腎臓など,いまでは臓器別にすらなった.対象がどんどん細分化されるのである.でも解剖は違う.解剖は対象ではない.だから「人体」解剖学とわざわざ言う.対象がカエルでも虫でもなく,人体だからである.他方,解剖学自体を解剖学の対象にすると「哲学だ」と言われてしまう.
では解剖とはなにか.方法である.日本の学問に方法論の意識が薄いのは,お気づきの人もあると思う.解剖という方法を学べば,解剖できる対象はいたるところにある.日本経済も政治も,解剖できないことはない.この場合の「解剖」は分析という意味であろう.分析もまた典型的な方法である.
解剖という方法をきちんと学べば,いたるところに応用が利くことがわかる.たとえ話で言えば,和洋中華は料理の分類だが,包丁の使い方は方法である.日本の諸科学は和洋中華のように分けられることが多い.でも包丁の使い方を知っていれば,和洋中華のどれであれ,料理の下ごしらえまではできる.
いま思えば,解剖学で学んだ方法を,解剖学自体に応用したのが,『形を読む』だった.つまり解剖学とは,私の場合,上の意味で基礎中の基礎だったのである.
意識と博物学
人体という対象を見て,なにかを考える.その時の人体は,当たり前だが,自然の産物である.では考えているほうはだれか.自分に決まっている.対象は何も言わない.従って対象から学んでいるのは,まさに自分である.
ではその自分とは何か.『形を読む』の最後は,だから脳で終わっている.それが続いて『唯脳論』(青土社)になった.そこではまだ「脳」と表現しているが,その実体は「意識」である.遺体には意識はない.私には意識がある.それが解剖学を成立させている.そこでは解剖学は意識と人体の相互作用である.
この本はしばしば誤解を受けた.脳が全てと言っている.そう解釈されたからである.それはむろん違う.意識が全てではないからこそ,問題が起こる.もう一度,全体を見直してみる,とくに身体をあらためて位置づけることが肝要ではないか.それが『唯脳論』の骨子だが,解剖学者が身体を重要だと言うのは,あまりにも当然であろう.
そこから続いて,私の問題は「意識」になった.意識は自然科学では禁忌になっていたと思う.日本ではいまでもその傾向があるのではないか.学者がそれをあまり考えようとしないように思えるからである.自然科学は「客観的」だという.客観とはだれの視点か.物理法則はいつでも,どこでも成立する.「私」の存在はそれには無関係である.そうした視点が成立するのは,じつは「神の視点」を採っているからである.一神教の世界から自然科学的な,「客観的な」思考が生まれ,進んでくるのは不思議ではない.それはどこまで本当か.物理法則の斉一性を主張しているのは,たとえば物理学者の意識である.この論法は無限循環を生み出す.なにを言おうが,すべては当人の意識の産物と言えるからである.だから学者はそれを避けるのであろう.
無限循環に陥らないためには,どうすればいいのか.ここでも解剖という方法がきわめて有用である.ヒトの意識はどういう具体的性質をもつか.まずそれを観察すればいい.動物の意識とはどこが,どう違うのか.そうした意識の解剖学,広い意味での意識の博物学が,『唯脳論』以降の私の関心事となった.『バカの壁』(新潮社)以降のシリーズは,じつは「意識の博物学」である.
この場合,博物学とは,自然の存在をありのままに見て,分類や解析をすることである.それが解剖学で私が学んだ方法である.系統解剖学はまさに分類学でもある.神経,血管,筋.それぞれの系統は,さらに細分される.なぜ人体はそうなっているのか.そうなっているから,仕方がないというしかない.
近代科学はこの「仕方がない」を嫌う.科学の世界では,すべてが説明可能でなければならないからである.説明不能だが明らかに存在すると思われるもの,たとえば意識がその最大の例だが,それは通常無視される.だから禁忌である.でも博物学という方法の優れた点は,その禁忌を一切無視できることである.博物学に禁忌はない.自然の中に存在するものは仕方がない.「あるものはしょうがない」のである.この考え方は,都市社会では通用しない.さまざまな災厄について,現代人は「あってはならない」とすぐに言うからである.さらに現代社会は説明可能なものだけしか身近に置かない.自分の身の回りを見ればわかることである.解剖学という方法を身に着けて,現代社会を生きるのは,だから意外に難しい.しばしば日常に差し支えることになるからである.
人体は自然である.意識的に構築されたものではない.それを扱うことは,上記のように都市社会の禁忌に触れる.都市は自然を排除するからである.そのことは解剖学会百周年記念のプラスティネーションの展示でも具体的によくわかった.学会百周年の委員会で展示を提案した時,「そんなものを見せていいんですか」という発言があったのを記憶している.その人自身は解剖学者だから,長年人体を見ているはずである.では一般人はなぜそれを見てはいけないのか.これは厄介な問題だから,短く論じることはできない.ともあれ展示は行われ,科学博物館での後の展示では,記録的な観客数となった.つまり人体の展示に対する社会的なニーズはきわめて高かったのである.
解剖学教室を引退してから,私は昆虫,とくにゾウムシの分類をやっている.これも方法はまったく解剖学である.博物学という大きなくくりをすれば,同じと言っていい.対象で考えると,人体と虫だから,まったく違うものだと思われてしまう.それが常識であろう.しかし方法論から言えば,むしろ「まったく同じ」である.子どもの頃の昆虫採集から八十歳を超えるまで,私自身は同じ作業を繰り返しているだけである.その方法を,解剖学は私に叩き込んでくれたと言ってもいい.そうした「方法」を身につければ,じつはいかなる対象もそれなりに扱うことができる.それが「解剖学は基礎中の基礎」の真意であろう.私はそう思っている.
解剖学実習
博物学はすでに死んだ学問と見なされているであろう.しかし上記のように,博物学的な作業は基礎中の基礎である.つまり自然界を観察する.さらにそこにあるものを記述することで,記述の仕方を学ぶ.
いまではデジタル機器が発達したので,観察は徹底的にと言っていいくらい様変わりした.私が現役だった時期は透過型電子顕微鏡の最盛期だった.現在では昆虫の観察でも,走査型電子顕微鏡はもとより,さまざまな顕微鏡が利用できる.さらに重要なことは,デジタルカメラの発達である.画素数が高いために,じつは普通の顕微鏡以上の性能を発揮する.ただしそのためには焦点合成を利用しなければならない.
カメラで対象を拡大すると,当然ながら焦点深度が浅くなる.深度が合った部分だけを合成し,パソコンで最終像を完成する.それによって,全体に焦点の合った虫の拡大像を得ることができる.最初にこの写真を見た時に,その正体がよくわからなかった.平面像ではないのに,全体にピントが合っている.そういうものは,これまでなかった.これをなんと考えたらいいのか.
そのうち落合陽一の「デジタル・ネイチュア」という言葉に出会って,なるほどと感心した.思えば,CT もMRIも,デジタル・ネイチュアである.どれもコンピュータによって合成された画像だからである.ただしそこには歪曲がない.自然の姿と見てもいい.これらは明らかに感覚の延長である.デジタル機器のおかげで,われわれは「目がよくなった」のである.
ところが目がよくなろうが,悪かろうが,ヒトが観察して記述する作業に変わりはない.拡大の問題点はすでに「形を読む」で指摘してある.対象を百倍に拡大すると,対象は百倍に大きくなる.つまり作業量で考えると,百倍見なければならない.一センチの虫は一メートルになってしまう.私が化学に親しめなかった理由の一つはここにある.分子を可視化するように描くと,細胞はあまりにも巨大になってしまう.そこを多くの人が考えていなかったと思う.なにかを精細に見ても,全体をその精細さで見るのはしばしば不可能である.科学の全体像が見えにくくなってくるのは,これにも関係があろう.
ともあれ,自然を対象として,それを観察し,記述する訓練はヒトの認識にとって,どうしても必要である.解剖学は歴史が古く,すでに多くの記述がなされている.私は教科書の改訂をする時,十九世紀の記述を多く読んだ.そこではっきりわかってくるのは,実物を見て記載しているか,過去の記述を利用して再記載しているか,の違いである.コピペという言葉ができたほどで,現代社会では情報の再利用が中心である.しかし実物を観察し,それを記述するのは,再利用とは違う.創造である.自然を言葉にするのだから,じつはこれが真の「情報化」である.しかしそれには手数がかかり,辛抱が必要である.だから若者には好まれない.実物から記述することは,情報の世界での一次産業である.一次産業はまさに基礎だが,それをやる人はどの世界でも少なくなった.だからこそ逆に重要性が増しているのである.
過去の記述を「済んだこと」にするのが現代だが,それはヒトが白紙で生まれてくるのを忘れているからである.ここにも解剖学実習の意味がある.分類学では新種を記載する.写真や図を付けたとしても,かならず記載文が必要である.百年前のそうした記載文を読むと,恐ろしいもので,分類学者の優劣がわかる.古典に学ぶとは,人を知ることである.
感覚と意識
上述のように,私は意識について考えるようになった.でも私は実験室を持っているわけではないし,意識学という学問分野が成立しているわけでもない.それなら博物学で行くしかない.その地域の虫を調べようと思ったら,まず虫を採るしかない.万事はそこから始まる.
ではうちのネコと私の意識の違いは何か.そうした考察の結果は『遺言』(新潮社)に書いた.すでに書いたから詳述はしない.ヒントになったのは,ネコつまり動物は,なぜ言葉を使わないのか,という疑問である.ある本で,調べられた限りの動物は,すべて絶対音感である,という記述にぶつかって気が付いた.絶対音感は聴覚の原理に近い.基本的には共鳴を原理にしているはずだからである.素直にそれに従えば,絶対音感になるはずである.ヒトがそうならない,つまり相対音感になるのは,感覚より意識が優先するからではないか.感覚を優先するなら,黒字で印刷された白という文字は読めない.黒に決まっているからである.そこからさらに進むと,人に固有の意識の機能がわかるように思われた.それはイコールという概念である.A=B であれば,B=A である.これは数学基礎論では交換の法則と呼ばれる.交換もまた,ヒトだけに特有であろう.レヴィストロースは,人類社会は交換から始まる,と述べた.むしろ「同じ」から始まるのである.そこから等価交換,つまりお金,さらに経済が生じる.ヒトとはDNA で98%以上同じとされるチンパンジーにも,おそらく=という機能はない.したがってチンパンジーに言語はない.交換もむろんない.認知科学で言われる「心の理論」もない.心の理論は社会的な相手と自分との交換の上に成立するからである.
詳細は既著に譲るとして,解剖学へ戻る.意識と感覚とを対比させたときに,再び解剖学の重要性に気づいた.頭の中でどう思おうと,しばしば感覚は否という.それが自然科学における実験の本来の意味である.ガリレオのピサの斜塔での「実験」は,そう思うと,意識と感覚の対比に見えてくる.意識は重い物体が先に落ちると予想するが,実際に落としてみると(視覚的には),軽いものと同時に落下する.
中世以来の欧州では,キリスト教神学が優越していた.それは理屈,つまり意識の優越である.しかし「実際に」確かめてみると,つまり感覚に訴えてみると,意識のほうを訂正せざるを得ない.では感覚を信じればいいのかというと,そうはいかない.反宗教改革を旗印としたイエズス会の本山,ローマのイグナチオ教会の天井画は,だまし絵になっている.それを見ていると,科学の時代になっても,イエズス会は頑張ったんだなあという気がしてくる.感覚が必ずしも正しいわけじゃありませんよ.だまし絵はそれを告げているようにも思えるのである.
ヒト個人の中で,感覚は外界を代表し,意識は内界を代表する.人そのものについて,いわば身体を外部化し,それを意識的に扱おうとするのが,解剖学である.この学問は本来,ヒトの錯覚を糺すものだとすら,私は考えるようになった.人体解剖学の対象はヒトであり,その場合にはヒトは外部化される.それを見る側が解剖学として再度内部化するのである.その作業によって,意識が持っている錯覚が矯正され得る.
なぜ解剖学なのか
最後は個人的な話題になる.医学部を出たのに,なぜ解剖学を選んだのですか.これは何回も訊かれた質問である.
素直に言えば,解剖という作業がいちばん安心だったからである.私は小学校二年生で終戦を経験し,その秋には当時の国語の教科書に教室で墨を塗った.私が言語表現をあまり信じなくなったのは,この体験が大きいと思う.一億玉砕,本土決戦は,平和憲法,民主主義になった.そのショックを想像するには,戦時下の人たちの雰囲気を知る必要がある.間違いないと信じていたものが,徹底的に覆される.それが私に与えた影響は大きかった.たとえば大江健三郎は二歳年上だと思うが.おそらく軍国少年から平和・民主主義者に変わった.私の場合は.どちらでもなくなったのである. どちらでもなければ,なにを信じればいいのか.面倒だが,すべてを自分で確認するしかない.解剖学実習はそれに答えてくれたのである.そこにはまったくウソがない.間違えたとすれば,それは私が間違ったのである.他のだれのせいでもない.その世界は私にとって,本当に安心だった. 私の世代のすべての人がそう思ったわけではないであろう.だからこれは個人的な出来事である.しかしだれであれ,なにか個人的な動機は持っているはずである.一つ指摘しておくとすれば,私の医学部の同級生の一割が基礎医学に進んだ.通常の学年なら,一人か二人である,教養学部のクラスでは,かなり多くの同級生が研究職を選んだ.その背景には,やはり確実なものを探そうという動機があったのではないだろうか.
戦後日本はモノ作りを得意とした.それにも同じような心理が働いたのではないか.作ったものがきちんと動かなければ,それは作った自分に責任がある.社会的な価値観が大きく揺らいだ時代に育つ若者たちは,モノに目を向ける傾向があるのだと思う.ヒトの社会は頼るに足りないと感じるからである.
そう思った時,私は似た世代を発見した.それは明治維新を子どもの年齢で通過した人たちである.北里柴三郎,志賀潔,野口英世など,医学界でも多くの人材が生まれている.もちろん育ちにより,時期にズレはあるだろうが,明治の日本が多くの科学者,技術者を生んだのは,上の意味で不思議ではない.
では現代はどうかというなら.若者に維新や敗戦の時のようなショックはないであろう.私が解剖を選んだ動機は,個人的であると同時に,社会的でもある.現代の社会的要因とは,なんであろうか.
だから私は自然に直面することを勧める.AIの世界はあくまでも補助である.それはヒトのためであって,AIのためではない.それは当たり前だが,うっかりするとダマされる.AIがヒトを置き換える.そんな主張がある.AIが置き換えるものは確かにある.それなら,それを自分の仕事にしなければいい.
すぐにわかることだが,ヒトが食っていくためにする仕事は,AIに置き換えられる可能性がある.経済的,合理的,効率的であればいいからである.学問も芸術も,その範囲には入らない.もともと「不必要」だからである.医学の中で,解剖学くらい,直接に実用の役に立たない分野は少ない.だからこそそれはヒトのする営為として大切なのである.まさにヒトでなければできないし,やらないからである.
大学紛争時,私はなり立ての助手だった.すでにCTが使われるようになっていた.そういう時代に,解剖学実習なんか不用ではないか.そういう意見を医学界の偉い先生から聞く機会があった.むろん私は反論した.いまでもその意見を変える必要を認めない.いまでは世界の8割のヒトが都市に住むという.自然に直面する機会はどんどん減っている.そうした都市環境で育つ若者たちは,どうなるのだろうか.
いま私がしていることは,子どもたちを集めて,野外に出すことである.感覚を通して,自然に直面させる.その訓練だけでいいと思っている.その子たちがどう育つのか,私はその答えを知らない.しかし少なくとも私はそうした自然環境の中で育った.それを将来の世代と共有したいと思っているのである.
(このページの公開日:2020年10月1日)